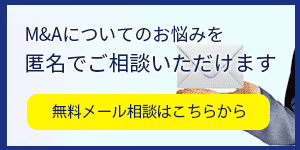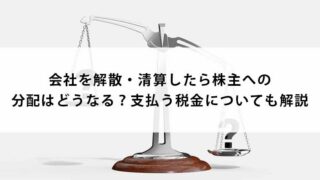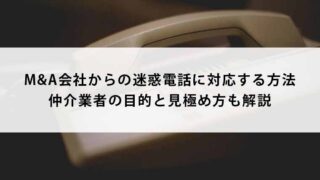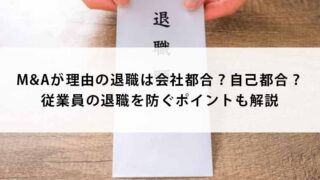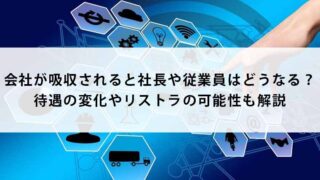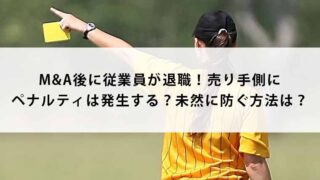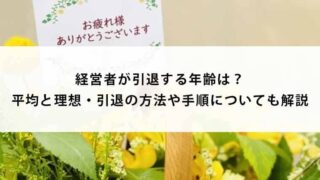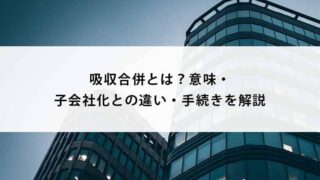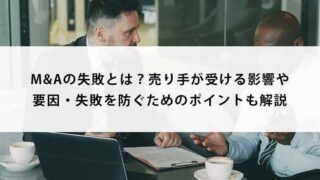M&Aに関する情報を集めていると「創業者利益」という単語を目にする機会も多いかと思います。
創業者利益とは、創業者が自社の株式を売却する際に得る利益を指しています。
しかし中には、2代目以降の経営者で「自分が創業者利益を受け取ることはできないのだろうか」という疑問を抱いている方もいらっしゃることでしょう。
そこで本記事では、創業者利益について、誰が受け取るかを含めた概要・目的・相場などを詳しく解説します。
より多くの創業者利益を得るためのポイントも紹介していますので、創業者利益について知りたい方はぜひ本記事をお役立てください。
登場人物紹介
インバースコンサルティング株式会社の代表取締役で現役のM&Aコンサルタントでもあります。記事内ではM&Aに関する疑問にどんどんお答えしていきます!
中小企業を経営している社長です。後継者不在に悩んでいて、M&Aを検討している真っ只中にいます。いつもは困った顔をしていますが、たまに笑顔になります。
1章:創業者利益とは

創業者利益とは、会社の創業者が所有する株式を売却して得る利益のことです。
創業した会社がIPOを果たしている場合は、株式を市場で売却して創業者利益を得ます。一方で創業した会社が非上場の場合は、M&Aで株式を売却して創業者利益を獲得します。
会社の株価は基本的に会社の業績に応じて増減するため、創業者が事業を成功させたことへの報酬が、創業者利益ともいえるのです。
ただし創業者利益は、全額がそのまま個人の利益となるわけではありません。
創業時の資本金・初期投資・会社売却にかかる手数料などの必要経費を考慮すると、株式の譲渡価格と諸々の必要経費の差額が実質的な創業者利益になると考えてよいでしょう。
1-1 2代目や3代目でも創業者利益を得られる?
創業者利益について解説しているサイトなどの多くは、創業者利益=創業者が自社の株式を売却して得る利益という部分までしか説明していません。
しかし創業者利益は、創業者から会社を引き継いだ2代目以降の経営者でも獲得可能です。
つまり、IPOやM&Aで経営者自身が所有する株式を売却して利益を得ることを創業者利益と捉えて差し支えありません。
1-2 創業者利益とキャピタルゲインの違い
キャピタルゲインとは、株式や債券などの保有している資産を売却して得られる利益です。
創業者利益も創業者が得るキャピタルゲインですから、広い意味で捉えると「創業者利益もキャピタルゲインの一種」となります。
2章:創業者利益を得る目的

創業者(もしくは2代目以降の経営者)が創業者利益を得る目的には、主に以下の4点が挙げられます。
- リタイアの費用にする
- 新規事業の資金にする
- 廃業を回避する
- 負債を清算する
それぞれの項目について、以下で詳しくみていきましょう。
2-1 リタイアの費用にする
中小企業の経営者が創業者利益を得る目的として多いものに、リタイア後の資金獲得が挙げられます。
悠々自適な老後を過ごすにはまとまった資金が必要なため、創業者利益を活用するのです。
創業者利益を資産運用に回せば、リタイア後もある程度の収入を得ながら生活することが可能になるでしょう。
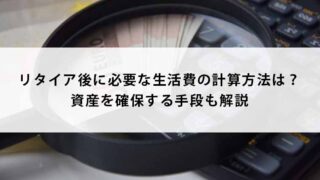
2-2 新規事業の資金にする
創業者利益を得る2つめの目的として、新規事業の資金獲得が挙げられます。
創業者利益を活用すれば、金融機関から新たに融資を受けることなく新規事業が始められます。
M&Aの契約内容によっては競業避止義務が発生するため同地域で同業種の事業は立ち上げられませんが、磨き上げたビジネスのノウハウは他業種でも充分通用するはずです。
こちらは主に、引退するにはまだ早い年齢かつチャレンジ精神旺盛な社長が取る選択肢ですね。
2-3 廃業を回避する
半数以上の中小企業が今、後継者の不在という大きな問題を抱えています。
これまでは親族内や社内に後継者を見つけられないと廃業を余儀なくされてきましたが、近年ではM&Aを活用して第三者へ経営権を譲渡することで廃業を回避する会社が増えています。
この場合は創業者利益の獲得というより、事業承継が一番の目的となっていることが多いですね。
廃業を回避して事業承継を実現したうえに、創業者利益まで得られるということですね。
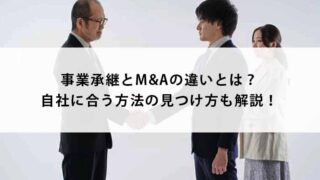
2-4 負債を清算する
4つめに挙げる目的は、会社経営によって積み重なった負債の整理です。
多くの経営者は、会社を経営していく過程で資金調達のために金融機関から融資を受けます。
たしかに弊社も金融機関から融資を受けています。
しかし業績が悪化し、廃業するにも融資の返済ができずに負債が残ることが予想され、廃業できない状態に陥っている会社が一定数存在します。
このような場合に負債の解消を目的として、創業者利益獲得を目指すのです。
さらに融資を受ける際には経営者が個人保証を背負う場合が多いため、万が一の際は経営者の個人資産が差し押さえられるリスクも背負っています。
そのため負債の清算とともに個人保証の解除もまた、創業者利益獲得の目的となり得ます。
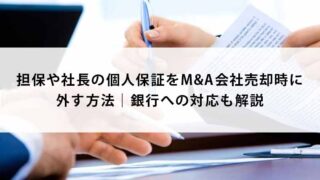
3章:創業者利益を得る方法
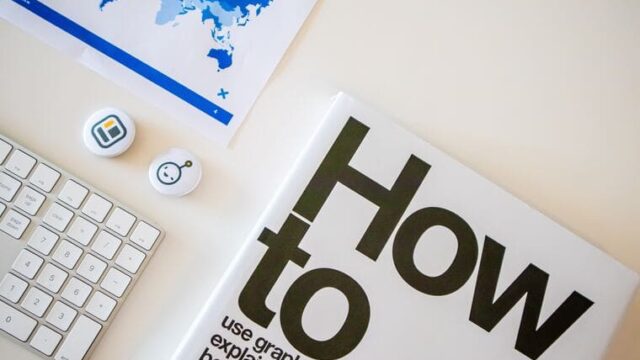
創業者利益を獲得するためには、経営者が保有する自社の株式を第三者に売却し、売却益を得なければなりません。
1章でも少し触れましたが、創業者利益を獲得するには、M&AとIPOという2つの方法があります。
ただし、自由に好きな方を選択できるわけではありません。2つの違いについて、以下で確認しておきましょう。
3-1 M&A
非上場企業の場合は、M&Aで経営者が株式を売却し、創業者利益を獲得します。
M&Aでは創業者自らが買い手を選べます。より良い条件で株式を売却できる相手を見つけて創業者利益の最大化を図れる点が、M&Aを活用するメリットだといえるでしょう。
またM&Aでは、経営者が所有している全ての株式を一括で売却します。まとまった金額の創業者利益を獲得でき、リタイア後の生活費や新事業への資金に充当しやすい点も特徴です。
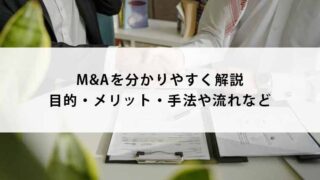
3-2 IPO
IPOは自社の株式を市場に公開し、証券取引所での売買を可能にすることです。
つまり、上場企業になるということですね。
IPOを果たし上場企業となった場合は、株式市場で自社の株式を売却して創業者利益を獲得します。
IPOにより自社の社会的信用度が上がり、優秀な人材を雇用しやすくなるなどのメリットを得られます。ただし上場には厳格な基準が設けられており、それらをクリアするために膨大な予算と期間を要する点がデメリットです。
また、経営者が所有する自社の株式を売却する際は、インサイダー規定に抵触する恐れがあるため注意が必要です。
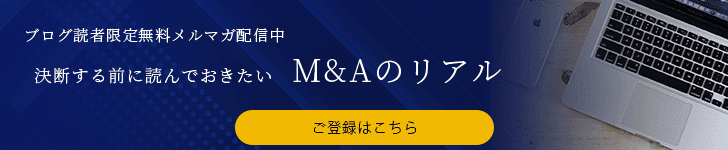
4章:創業者利益の相場はいくら?

創業者利益の獲得を目指す際に気になる点として、手に入れられるおおよその金額が挙げられます。
しかし実は、創業者利益には明確な相場がほとんどありません。なぜなら株式を売買する価格は、それぞれの会社が持っている企業価値や市場の状況によって、大きく変動するからです。
とはいえ、ある程度の目安は必要です。一般的にM&Aで創業者利益の獲得を目指す際には、取引価格の目安を以下の計算式で算出します。
時価純資産額+営業利益2~5年分
ご存知の方も多いかと思いますが、IPOの場合は市場の取引価格に従います。
株式市場での取引ですもんね。他の投資家と条件は同じということですね。
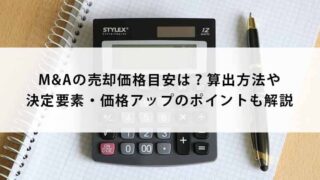
5章:創業者利益にかかる税金
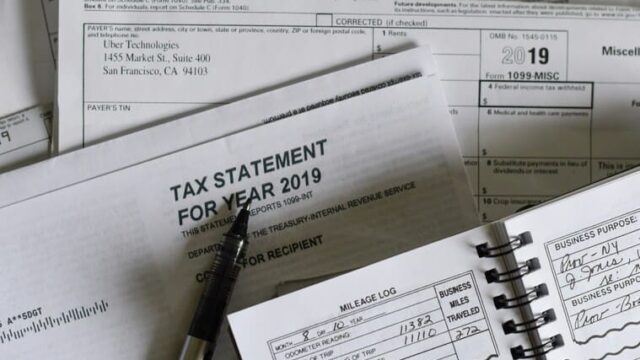
創業者利益にかかる税金は上場・非上場を問わず譲渡所得に該当し、他の所得と合算することなく創業者利益にかかる税金だけを単独で計算します(分離課税)。
譲渡所得に課税される税率は、以下の通りです。
所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=20.315%
ただし、株式を売却して得た金額がそのまま課税対象となるわけではありません。課税対象となる譲渡所得は、以下の計算式で算出します。
譲渡所得=譲渡価額ー(株式の取得価額+手数料などの経費)
株式の取得価額とは、売却対象の株式を過去に自分が取得したときに支払った購入代金のことで、創業者の場合は出資金(資本金)が該当します。
ちなみに取得価額には、購入手数料・消費税・名義書換料などその株式を取得するために要した費用も含まれます。
手数料などの経費とは、会社売却の際にM&A仲介会社や士業事務所などへ支払った手数料を指します。
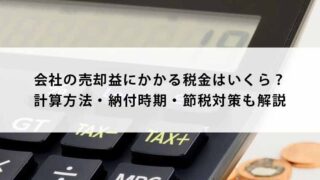
6章:M&Aでより多くの創業者利益を得るためのポイント

M&Aでは、工夫や努力でより多くの創業者利益獲得を目指せます。ポイントは、主に以下の4点です。
- 適切なタイミングでM&Aを行う
- 企業価値を高める
- 持ち株比率を100%に近づけておく
- 専門家に相談する
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
6-1 適切なタイミングでM&Aを行う
M&Aで株式を売却する際もIPOと同じく、市場の動向によって価格が左右されます。そのため価格が上昇しているときに売却すると、より多くの創業者利益を獲得できるのです。
非上場企業が市場の動向を知るためには、同業の上場企業の株価推移を確認すると良いでしょう。業界全体で株価が上昇傾向にあるときが、売却のタイミングだといえます。
さらに、会社が成長を続けている時期は、より多くの創業者利益を獲得できる可能性が高まります。
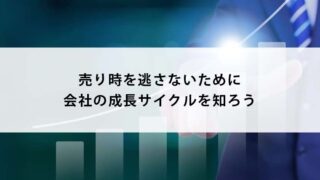
6-2 企業価値を高める
全ての商品にいえることですが、価値の高い商品には高い価格が付きます。たとえ価格が高くても、価値が高い商品には「欲しい」と思わせる魅力があるからです。
M&Aも同様に、価値の高い企業は高い価格で取引される傾向にあります。そのためより多くの創業者利益を得たいならば、自社の企業価値を高めることが効果的です。
企業価値を高める要素としては、主に以下の4点について検討すると良いでしょう。
- 独自の技術・ノウハウ
- 優秀な従業員
- 魅力的な「仕組み」
- 企業理念・企業風土 など
上記の項目について検討する際には、自社の強みを洗い出す作業が効果的です。その強みを磨き上げることで、企業価値を高められますよ。
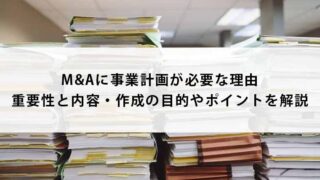
6-3 持ち株比率を100%に近づけておく
M&Aによる創業者利益を最大化するためには、経営者自身がなるべく多くの株式を所有している必要があります。
なぜなら、買い手となる企業のほとんどは、売り手対象企業の100%の株式取得を目指しているからです。
とはいえ中小企業の場合は、経営者(オーナー)が100%の株式を所有しているケースが多くを占めているため、あまり問題にはなりません。
しかしながら、経営者自身の知らぬところで他に株主が存在している会社が存在することも事実です。
特に、先代から経営を引き継いだ2代目以降の経営者は注意が必要です。
創業者利益の獲得へ乗り出す前に全ての株式について所有者を明らかにし、必要に応じて持ち主から買い取るなどの対応を実施してください。
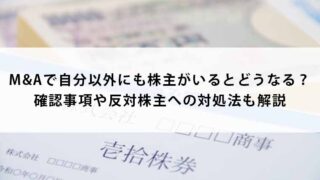
6-4 専門家に相談する
M&Aでより多くの創業者利益を得るのであれば戦略的な売却活動を展開しなければなりませんが、そのためには高度な専門知識と豊富な経験が求められます。
しかしながら売り手の多くはM&Aの経験を持たない経営者であるため、必要に応じて専門家のサポートを受けると良いでしょう。
創業者利益の獲得を検討し始めた際には早い段階で複数の専門家へ相談し、信頼できるサポーターを見つけてください。
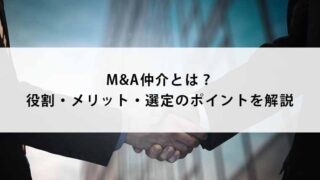
まとめ
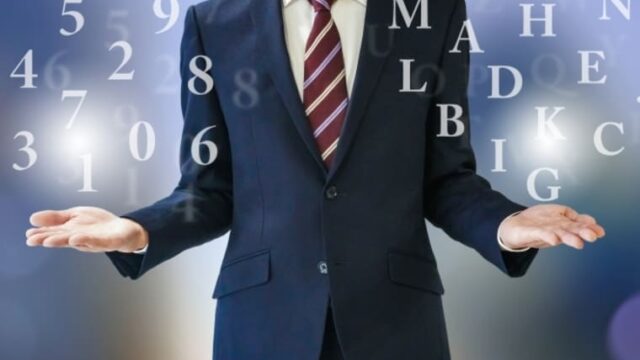
創業者利益とは、会社の創業者が所有する株式を売却して得る利益のことですが、「会社の経営者」が所有する株式を売却して得る利益とも言い換えられます。
つまり、2代目や3代目であっても、創業者利益の獲得が可能です。
創業者利益を獲得するにはM&AとIPOの2つの方法がありますが、中小企業の場合はM&Aを活用するケースが多くなっています。
より多くの創業者利益を獲得するには、適切なタイミングの見極めや企業価値の向上など、いくつかのポイントをおさえてM&Aを実行することが重要です。
そのためには早めに信頼できる専門家を見つけ、サポートを依頼すると良いでしょう。
M&Aの相談は、いつでも無料で受け付けています。匿名で承りますので、お気軽にご相談くださいね。
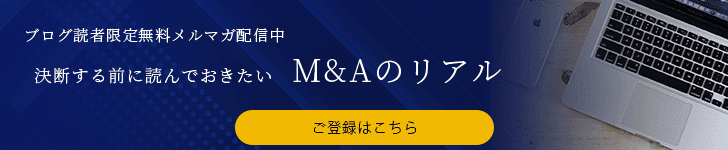
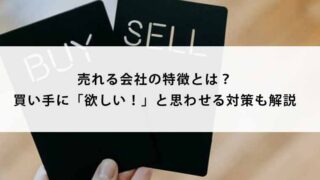
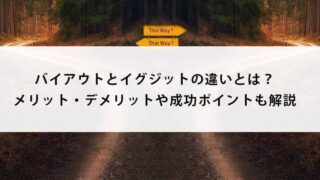
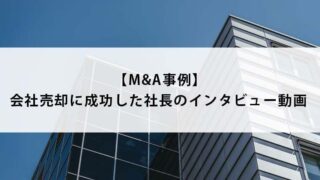
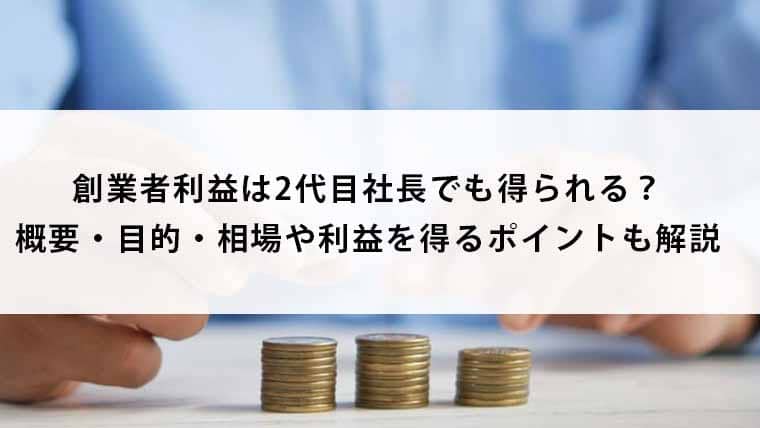
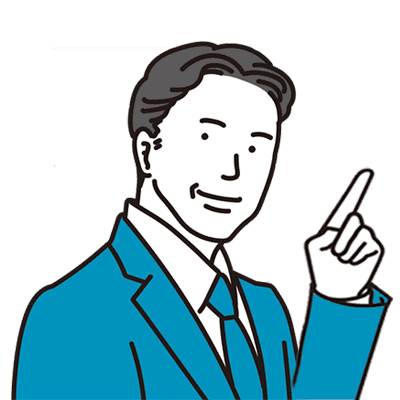
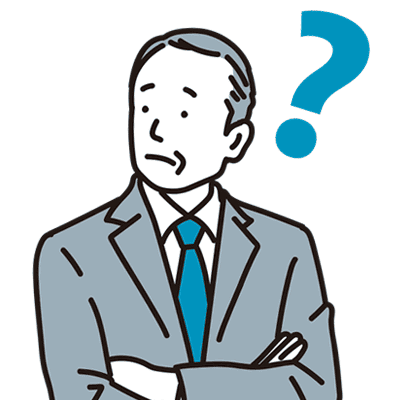
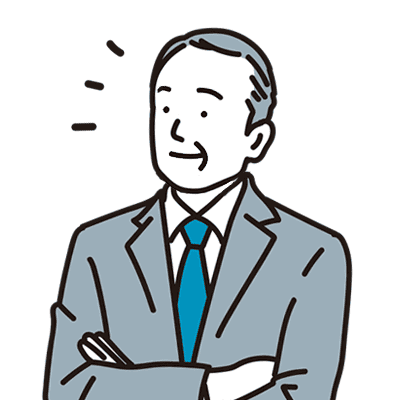
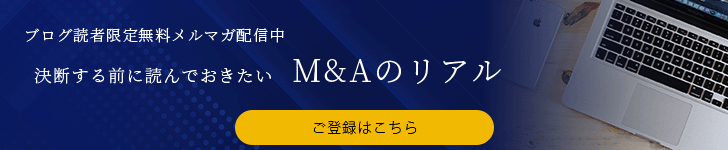
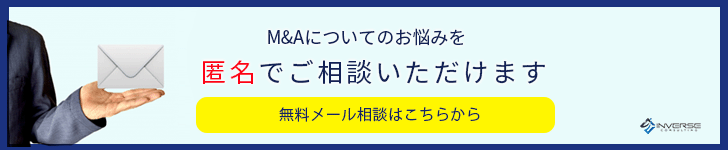
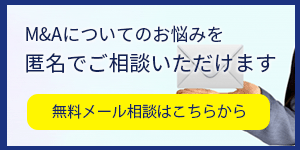
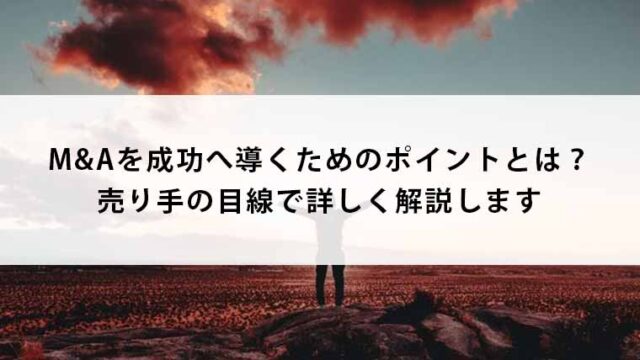
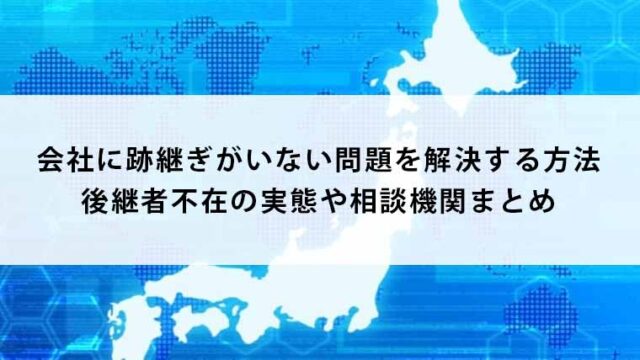
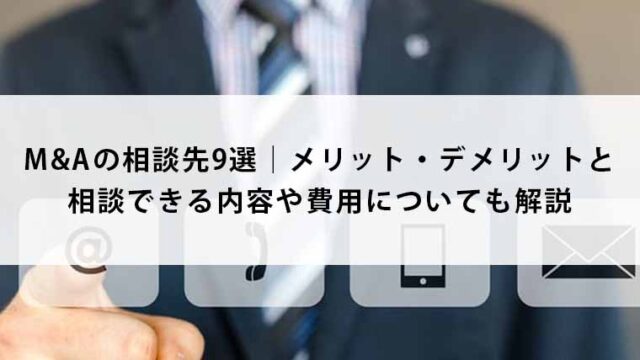
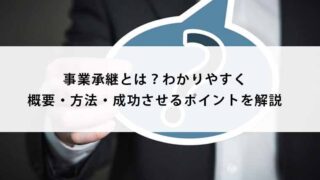
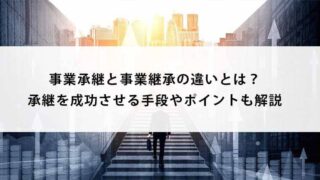
2.png)